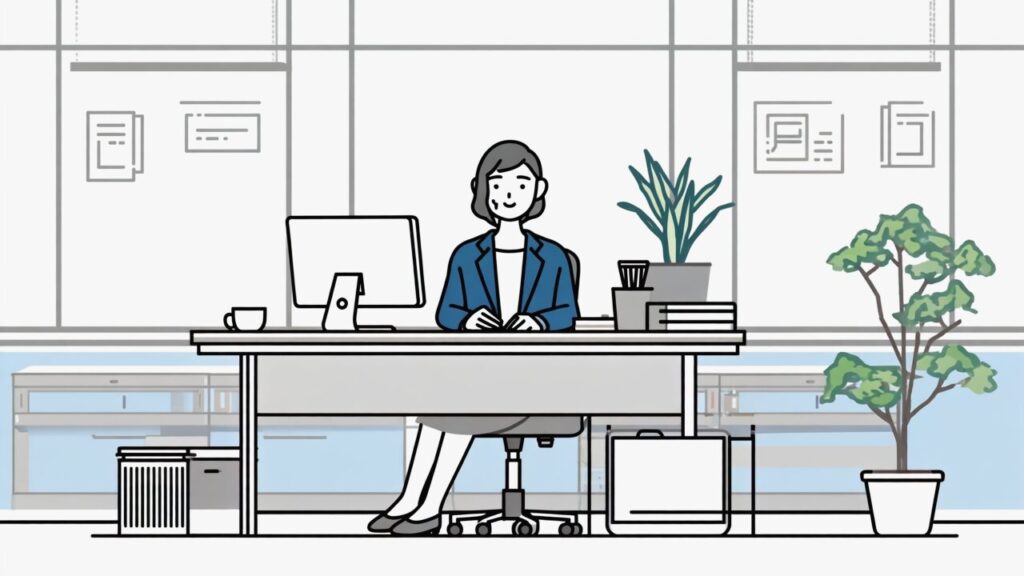
「社会人になったけど、どんな本を読めばいいかわからない」「成長したい気持ちはあるけれど、本選びにいつも迷う」
そんな声を、私は何度となく部下との面談で耳にしてきました。私は現在、40代の中間管理職として、幅広い年齢層の社員と日々接しています。彼らの多くが「本を読みたいけど、何を読んだらいいのかわからない」と悩んでいるのです。
この記事では、「本選び」そのものよりも先に知ってほしい「本の読み方」と「効率的な読み方」についてお伝えします。特に、社会人1年目やスキルアップを目指しているあなたに、読書の第一歩を踏み出すためのヒントになれば幸いです。
その本から何を得たいか目的を持とう
「とりあえずビジネス書を読もう」と思って書店に行ったものの、どれも似たように見えて選べない。そんな経験はありませんか?
これは、「目的が定まっていない読書」の典型です。実は多くの人が、「なんとなく読まなきゃ」という気持ちで本を選び、時間だけが過ぎていきます。
読書をする前には、ぜひ「この本から何を得たいのか」を自分に問いかけてみてください。
たとえば──
- 「論理的に話せるようになりたい」
- 「マネジメントの基礎を知りたい」
- 「時間の使い方を見直したい」
このように読書の目的を明確にすることが、内容の理解や行動への落とし込みにつながります。
小説以外は“全部読もうとしない”のが正解
多くのビジネスパーソンがやりがちなのが、小説と同じようにビジネス書を最初から最後まで一言一句読もうとすることです。これでは時間がいくらあっても足りませんし、効果も薄くなります。
読むべきは「全部」ではなく、「必要な部分」です。
読み方のコツ
- 概要を知りたいとき → はじめに・おわりに だけ読む
- 要点を拾いたいとき → 「しかし」「つまり」「結論は」などに注目
- 記憶に残したいとき → 誰かに教えるつもりで読む(定着率+28%)
- 学びを深めたいとき → 白紙に書き出しながら“思い出す”ことで理解が定着
「速読」に踊らされないで
「1冊5分で読める!」といった速読の情報もネットには溢れています。しかし、世界最先端の研究では、その効果はほぼ否定されています。
科学的にわかった“速読の真実”
2016年、カリフォルニア大学の研究チームが145のデータを分析した結果──
- 読むスピードを上げると、理解度はむしろ下がる
- 目の動きなどがスピードに与える影響は10%未満
つまり、写真のように本を「眺める」ような読み方では、ほとんど頭に残らないという結論が出たのです。
「何を読むか」ではなく「どう読むか」で差がつく
たとえば、次のように考えてみてください。
| 課題・悩み | 読書目的 | 読み方 |
|---|---|---|
| 上司との会話が続かない | 雑談力をつけたい | 導入と結論だけ読む |
| プレゼンが苦手 | 論理的に話したい | 要点だけ拾って読む |
| 成長実感がない | 自己理解を深めたい | ノートに書きながら読む |
こういった具体的な目的をもって読むことで効率的に読むことができます。
一言一句読まなければ、と考えてしまうとやはり読書のハードルが上がってしまいます。
社会人におすすめの「はじめの2冊」
今回は本の読み方を知ることが大切とした場合次の本を読んでみることをおすすめします。
知識を操る超読書術
まずは本の読み方を学びたい人へ。
事例を交えて説明があるため読みやすい。
読書の技法
読んでいて知識を操る超読書術の元となったんだろうなと思える本。
こちらは本格的に本の選び方(読まなくていい本を見分ける)ことまで記載されていますがやや読書の難易度高め。
まとめ|読書はスキル。やり方を学べば一生使える
社会人の読書は、単なる趣味や自己満足ではありません。「自分を変えるためのツール」であり、使い方次第で人生に差がつきます。
何を読むかに迷う前に、まずは「読書の考え方」と「読み方」を見直してみてください。
「時間がないからこそ、正しく読む」
「本を読み切らなくても、成果は出せる」
このマインドを持つだけで、読書はもっと気楽に、もっと実践的になります。



